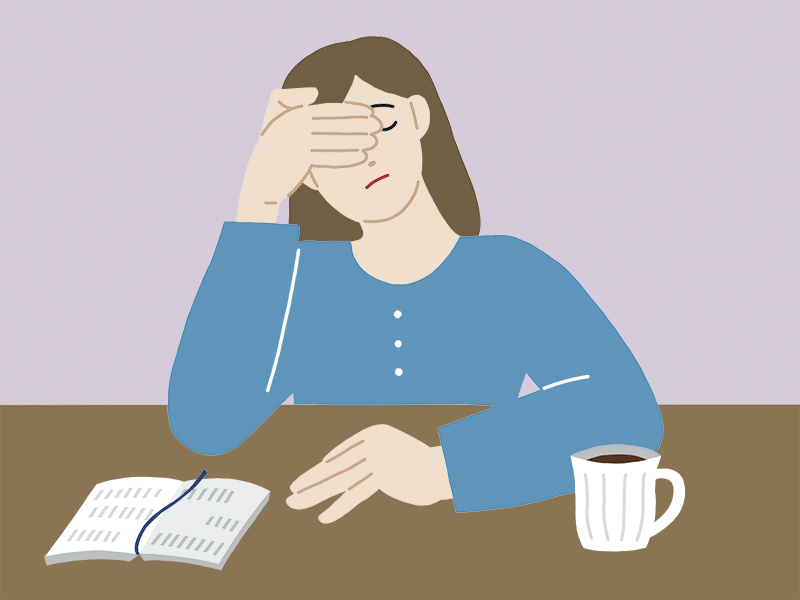ビタミンB1は水溶性ビタミンの一種で、糖質を体内でエネルギーとして使う際に重要な役割を果たしています。
十分に摂取できていないとエネルギー不足となって体に影響を及ぼすため、意識して摂りたい栄養素の一つといえますね。
この記事では、ビタミンB1のはたらきや多く含まれる食べ物、健康のために必要な摂取量などについて詳しく解説します。
1.ビタミンB1とは
ビタミンB1は食べ物や飲み物に含まれる「糖質」を体内でエネルギーに変えるのに不可欠な栄養素です。
糖質からエネルギーを生成するために必要なビタミンB1は、脳や神経系が正常にはたらくためにも重要な役割を担っているといえますね。
またビタミンB1には皮膚や粘膜の健康維持を助けるはたらきもあります。
【関連情報】 「ビタミンB1とは?作用や食事摂取基準、摂取源となる食品を紹介」についての記事はこちら
2.ビタミンB1を豊富に含む食べ物
ビタミンB1は動物性食品では肉類や魚介類など、植物性食品では穀類や豆類などに多く含まれています。
ここからは、ビタミンB1を効率的に摂取できる食べ物を動物性食品と植物性食品に分けてご紹介していきましょう。
2-1.ビタミンB1を豊富に含む動物性食品
ビタミンB1は動物性食品では豚肉などに多く含まれています。
| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |
|---|---|---|
| 豚ヒレ肉(赤肉) | ||
| 豚もも肉(脂身付き) | ||
| 生ハム | ||
| 豚ロース肉(脂身付き) | ||
| うなぎ | ||
| 豚肩ロース肉(脂身付き) | ||
| たらこ | ||
| ロースハム | ||
| 豚ひき肉 |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
「普段肉類はあまり摂れていないかも……」
という方は意識して普段の食事に取り入れてみると良いでしょう。
2-2.ビタミンB1を豊富に含む植物性食品
ビタミンB1は、種子類ではごまなど、豆類では大豆など、大豆、また玄米などにも含まれています。
| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |
|---|---|---|
| ごま | ||
| 大豆(国産・黄大豆) | ||
| カシューナッツ | ||
| あずき | ||
| らっかせい | ||
| 玄米 | ||
| 干しそば |
文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成
乾燥させて水分が抜けたごまや大豆などは、同じ重さの他の食品と比較するとビタミンB1の含有量が多くなっていると考えられます。
1回当たりの摂取量は多くはありませんが、おかずやごはんに混ぜたり振りかけたりすれば手軽にビタミンB1の摂取量を増やすことができそうですね。
また普段食べているごはんや食パンを玄米やライ麦パンなどに変えることでも、ビタミンB1を多く摂取できますよ。
【関連情報】 「ビタミンB群」についてもっと知りたい方はこちら
3.ビタミンB1の不足や過剰摂取による影響
ビタミンB1が不足するとどうなるのか、反対に摂り過ぎてしまった場合に体に悪影響がおよばないか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここからはビタミンB1の不足や過剰摂取によって起きる体への影響について説明していきましょう。
3-1.ビタミンB1の不足による影響
ビタミンB1が不足すると糖質を摂取してもエネルギーに変えられず、エネルギー不足になってだるさや疲労を感じるようになります。
普段の食事から十分にビタミンB1を摂取できていない状態には注意が必要です。
また、糖質やアルコールの摂り過ぎによってより多くのビタミンB1が消費され不足してしまうケースもあります。
ビタミンB1の不足が深刻になると、エネルギーとして糖質を必要とする脳や神経系にも影響を及ぼすことがあります。
その代表的な例が「脚気(かっけ)」という病気です。
脚気はビタミンB1を多く含む玄米から白米を主食とするようになり副食が不足していた明治時代には「国民病」と呼ばれるほど広くみられていた病気でしたが、副食からビタミンB1を摂取できる現代では少なくなっています。
しかし、極端な偏食やインスタント食品・アルコールから糖質を摂り過ぎることが原因でビタミンB1不足となり発症する方もいるようです。
ビタミンB1を食べ物から十分に摂取することはもちろん、糖質の量など全体的な栄養バランスを意識することが重要だといえますね。
3-2.ビタミンB1の過剰摂取による影響
通常の食品を摂取していてビタミンB1の過剰摂取から体に悪影響が生じたという報告はこれまでにありません。
ただし、ビタミンB1の一種である「チアミン塩化物塩酸塩」を長期的に過剰摂取した際に、頭痛や不眠、かゆみなどが生じたケースが報告されています。
しかし、十分なデータが得られていないことから摂取量の上限は設けられていません。
このため、ビタミンB1の摂り過ぎを極端に気にする必要はないといえるでしょう。
【関連情報】 「栄養バランスの取れた食事」についてもっと知りたい方はこちら
4.ビタミンB1の食事摂取基準と摂取状況
「エネルギー不足にならないためには、1日にどのくらいの量を摂取したら良いんだろう?」
「普段の食事でビタミンB1は足りているのかな?」
現代では深刻なビタミンB1欠乏症は少なくなったといっても、普段の食事で十分に足りているのか気になりますよね。
ここでは、ビタミンB1を摂取する目安となる量と日本人の平均的な摂取量をご紹介します。
4-1.ビタミンB1の食事摂取基準
各栄養素の摂取量の目安として、厚生労働省は「日本人の食事摂取基準」を公表しています。
この基準では、1歳以上の年齢層には「推定平均必要量」と「推奨量」が、1歳未満の乳児に「目安量」が設定されています。
ビタミンB1の推定平均必要量は以下のとおりです。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1〜2歳 | ||
| 3〜5歳 | ||
| 6〜7歳 | ||
| 8〜9歳 | ||
| 10〜11歳 | ||
| 12〜14歳 | ||
| 15〜17歳 | ||
| 18〜29歳 | ||
| 30〜49歳 | ||
| 50〜64歳 | ||
| 65〜74歳 | ||
| 75歳以上 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
ビタミンB1の推奨量は以下のとおりです。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1〜2歳 | ||
| 3〜5歳 | ||
| 6〜7歳 | ||
| 8〜9歳 | ||
| 10〜11歳 | ||
| 12〜14歳 | ||
| 15〜17歳 | ||
| 18〜29歳 | ||
| 30〜49歳 | ||
| 50〜64歳 | ||
| 65〜74歳 | ||
| 75歳以上 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
ビタミンB1の目安量は以下のとおりです。
| 月齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 0〜5カ月 | ||
| 6〜11カ月 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
また通常より多くの栄養素が必要になる妊娠中・授乳中の方については、年代別の推奨量に対し以下の付加量が設定されています。
| 妊婦 | |
|---|---|
| 授乳婦 |
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をもとに執筆者作成
4-2.ビタミンB1の摂取状況
ビタミンB1を普段の食事で十分に摂取できているのか、それとも意識してさらに多く摂取した方が良いのか、気になるところですよね。
厚生労働省が実施した「令和元年 国民健康・栄養調査」によると、ビタミンB1の1日当たりの平均摂取量は以下のとおりです。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1〜6歳 | ||
| 7〜14歳 | ||
| 15〜19歳 | ||
| 20〜29歳 | ||
| 30〜39歳 | ||
| 40〜49歳 | ||
| 50〜59歳 | ||
| 60〜69歳 | ||
| 70〜79歳 | ||
| 80歳以上 |
厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」をもとに執筆者作成
ビタミンB1の摂取状況を見ると、14歳以下の子どもや70歳以上の高齢者では、平均摂取量が推奨量をおおむね満たしているか、それを上回っている傾向があります。
一方で、20〜39歳の女性や15〜59歳の男性では、平均摂取量が推奨量をわずかに下回っており、不足気味の傾向が見られます。
食事摂取基準と国民健康・栄養調査では年齢区分が異なるため、単純な比較はできませんが、全体の傾向をつかむ参考としてくださいね。
働き盛り世代は意識してビタミンB1を摂取することが推奨されます。
【関連情報】 「ビタミンB6の食事摂取基準」についてもっと知りたい方はこちら
5.ビタミンB1を含む食べ物についてのまとめ
ビタミンB1はビタミンB群の一種で、糖質をエネルギーに変えるはたらきに欠かせない栄養素です。
糖質は脳や神経系の主要なエネルギー源であるため、これらの器官が正常に機能するためにも重要だといえます。
ビタミンB1は動物性食品では肉類や魚介類、植物性食品では穀類や豆類に含まれています。
動物性食品では特に豚肉に豊富に含まれています。
また植物性食品では大豆やらっかせい、あずきなどから摂取できます。
玄米ごはんやライ麦パンにも含まれているので主食を置き換えることでも摂取量を増やせますよ。
ビタミンB1が不足するとエネルギー不足に陥り、だるさや疲労感を招いてしまいます。
ビタミンB1の平均摂取量は男女とも多くの年代で推定平均必要量を若干下回っているため注意が必要です。
特に糖質の摂取量が多い方は、前述の食品などから意識的にビタミンB1を摂取してくださいね。

執筆者 メディパレット編集部
私たちは「健やかな未来を、ここから。」をコンセプトに、健康に関わる情報メディア“Medipalette”を運営しています。